イベントレポート:広島工業大学高等学校 K-STEAM類型 2024年度 探究発表会・卒業製作展
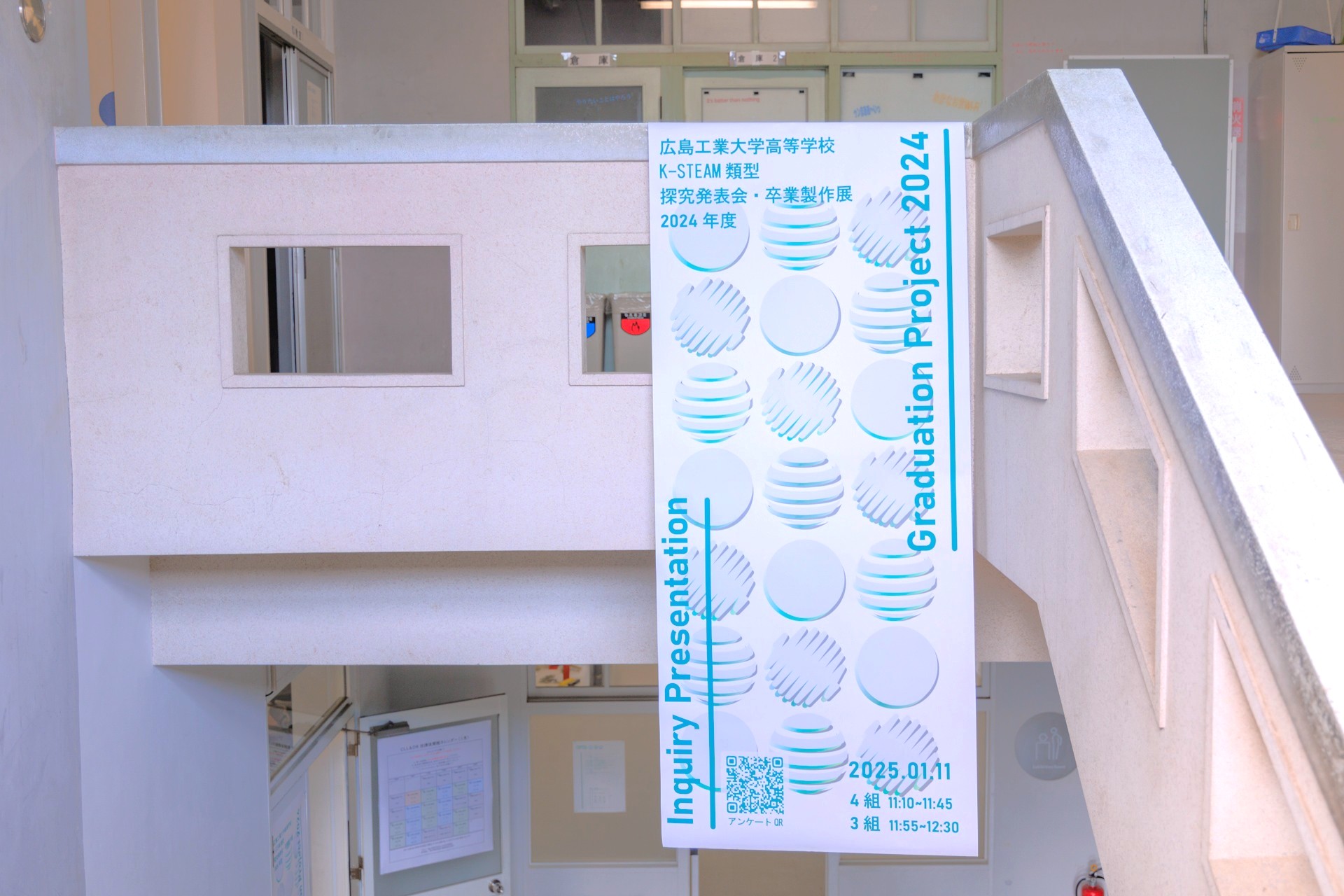
当社では、広島工業大学高等学校に常駐しながら、STEAMカリキュラムの進行支援をしています。校内にはデジタルファブリケーション機器を扱う工房「クリエイティブ・ラーニング・ラボ」があり、授業や放課後利用が可能。スタッフが常駐し、先生方や、生徒たちが考えるものづくりをサポートしています。今回はその広島工業大学高等学校で行われた発表会の様子をサポートスタッフよりお伝えします。
どんな展示だったか
2025年1月に「K-STEAM類型2024年度 探究発表会・卒業製作展」が行われました。K-STEAM類型は、2022年4月にスタート。「たまらなく好きなものを見つけ、夢中になる」というコーススローガンのもと、デジタル工作機器を揃えた工房での“ものづくり”などを通じ、理工系マインドを育てるコースです。今回の発表展示は、K-STEAM類型1期生となる学生たちが3年間過ごしてきた集大成となる展示会。進路について探究を行った内容や、自主製作として進めていた活動をまとめた内容など、約1年かけた取り組みについて発表しました。

会場には、発表を行う3年生や教員に加え、K-STEAM類型の1・2年生も鑑賞に訪れました。3年生にとっては、3年間の集大成を披露する場。後輩たちの期待や憧れの眼差しを受けながらも、堂々とのびのびと発表する姿が印象的で、その成長が感じられました。
1・2年生も自分たちの場合は何を作ろうかと想像を膨らませながら鑑賞していた様子でした。 これまで3学年合わせての交流は行われてこなかったため、K-STEAM類型の生徒たちにとっては、学年を越えた交流が新鮮に感じられたよう。K-STEAM類型の学年を跨いでの交流は、程よい緊張感と期待に満ちていました。


製作展についての感想アンケートによると、純粋に展示作品を楽しんだり、感嘆の声を漏らしたり、そして工房を活用して制作したいことについて想像を膨らませたりと、モノづくりのきっかけとなる良い刺激を受ける機会となった様子でした。
生徒作品紹介
発表されていた多くの作品の中から、いくつかをピックアップして紹介します。
「3Dプリンターでつくるランプシェード」
モデルのパラメーターとそれらの関係を定義して、変更しやすいデザインを作成していく「パラメトリックモデリング」を用いて制作する方法を探究していました。ノードベースの形状設計ツールの「Nodi」を使用して製作を行っています。粒の連なった形状から漏れ出す光がきれいです。


「組立式机」
ボンドや釘などの留め具を使用せずに組み立てることのできるミニチュアの机です。試作を重ね、組み立てる際にどれだけ接合部をシンプルに、かつ強固に作れるか意識して製作しました。大学に入ったら実寸大のサイズで製作するそうで楽しみです。


「3Dプリンターによるスネアドラムの制作」
スネアドラムのシェルを3Dプリンターを活用して製作。一般的なスネアドラムと比べ、重量が軽くなったため打音に変化があったそうです。3Dプリンターの密度の設定を高密度にすることで、音の響きを追求。鑑賞者は実際に体験することで音色を楽しんでいました。


「VR・3Dプリンターを活用した建築デザイン」
3DCADソフト「SketchUP」を活用して夫婦と子ども1人の3人家族の住まいを想定した平屋を設計しました。VRでは視点の高さを設定することが可能なため、空間に没入して体験することができます。また、3Dプリンターでは家の間取りをわかりやすくするため、様々なアプローチの方法を取っています。


「流浪の猫」
男性が謎のヘッドホンを貰い、異世界へ猫として転生する3DCGアニメーションです。VFXを活用して実写の人間を撮影し、その後3DCGソフトのBlenderで作成した3DCG空間内へ合成して映像を製作しました。猫が歩くシーンでは、対象の猫を追いかけるようにカメラワークが動いており、冒険のわくわく感があります。


「昆虫の標本を箱から作る」
レーザーカッターで作ったA4サイズの木製標本箱です。カブトムシとノコギリクワガタについて、説明文や実物を展示しています。標本を製作する前のイメージスケッチを作成し、標本箱の内部に入れるもののサイズや余白を考慮してきれいに仕上げていました。


「永久こま」
ネジ釘に巻いたコイルを乾電池により磁石にして永遠に回り続けるコマを製作しました。電磁石とコマの磁力の吸引と反発を利用し、コマが加速して回り続ける状態を体験することができます。


「廃材を利用してカホンを作る」
工房に余っていた板材を大型CNCのShopBotで切り出し、叩くとバス音が鳴る打楽器を製作しました。写真右にあるのが廃材となっていた板材です。木材をヤスリがけし、手触りを追求。木目が出ており、美しい仕上がりになっています。音が鳴る様子には皆さん興味津々でした。


サポートスタッフの目から
【年間を通した授業の様子】
4月末から、生徒たちは各自進路に関連するテーマを設定し、探究や制作を開始しました。しかし1学期中は自身の進路先について迷う生徒も多く、なかなか制作テーマや制作物が決まらない生徒もちらほら。まずは、自身がやりたいことを学ぶ進路先を1つ決めるための情報収集に取り組む様子が目立ちました。

進路先や、自身が必要とするスキルが決定した生徒は製作物についてアイデアスケッチや必要素材をピックアップを行い、プロトタイプを進めます。授業時間では教員やスタッフとヒアリングを通して制作工程を確認したり、制作の中で起こった問題の対処を行っていきました。
7月と9月には中間発表を実施。自身が製作していくものの表明、そして製作の進捗や、完成目安となる日程を発表していきました。この時期は推薦受験や受験準備を進める生徒も多く、なかなか作品が完成する目途が立たない状態の方も多かったため、少々不安でした。そのため、この後の授業では製作を完成とするラインを各生徒さんと話し合いを行い、進捗報告などもこまめに実施するよう進めていくことに。
11月初旬に行われた学校祭を終え、推薦受験を迎えた生徒たち。後期になると余裕が出てきて、製作にも打ち込む様子が見られました。この頃、先生とスタッフの間でも「完成した作品を展示し、他者へ体験や鑑賞していただく機会を持ちたい」と卒業製作展についても計画を立て始めました。

進路についての製作を終えた生徒はさらに、11月から自身が制作したいものや探究したいテーマを設定して卒業制作を行いました。そのため、当日の展示作品は進路についての作品を各自1点以上展示し、卒業制作まで行った生徒はその作品も同時に設置するという内容で配置しました。


展示会当日までの準備として、生徒たちは、作品の完成に加え、キャプションと製作レポートの記述と提出、会場へ展示する設営計画の考案を行いました。スタッフと教員は、生徒の進捗把握と共にヒアリング、他学年を展示へ招待する準備、当日の流れなどを決めていきました。スタッフとしては先生方のサポートとして展示のゾーニング、当日のパンフレットやメインビジュアルの作成など、展示会へ向けて準備を進めていきました。12月の放課後は発表に向けて工房で作業をする生徒が多かったです。


【発表時の3年生の様子】
3年生同士でも、自身の作品に打ち込んでいた生徒さんが多かったため、展示リハーサルや当日に他の作品を初めて鑑賞される方も少なくなく、1年間打ち込んできたものの成果にお互いに興味津々といった様子でした。
また、ゲーム製作や電子工作、楽器などの体験できる作品には、成果発表の場が盛り上がっていました。鑑賞者も、作品が狙い通りの成果を上げているかを実際に確かめられるため、評価しやすかったようです。
PCを設置しているDesign Roomでは、ゲームやプログラミング、映像を制作した3年生がメインに展示を行っていたため、多くの鑑賞者が集まってそれぞれ作品のプレイを楽しんでいました。


【発表後の記録】
2月末には1期生の過ごした3年生の活動記録として、73人分の作品を先生方と協力して冊子を製本してまとめました。この冊子には、3年間の製作物の中で思い入れの深いものや、しっかり取り組んで制作したものなど、それぞれの「あそび心」やこだわりを詰めた作品が集まっています。

まとめ
今回は1期生ということで、K-STEAM類型初の卒業製作を含めた展示会を実施しました。発表者それぞれのスタイルで展示発表し、鑑賞者の皆さんは好奇心旺盛に体験していました。また、鑑賞者だけではなく発表者同士も作品を通して交流を深めている様子もあり、会場内は心地の良い雰囲気を感じ取れました。先生方も生徒たちも初めてのことに挑戦しながら作り上げていくことができたため、成果は大きかったなと実感しています。
私自身も、このような場を一緒に作り上げていくことができる機会にとても感謝しています。これからも、K-STEAM類型の生徒さんのご活躍を応援しています
協力 : 広島工業大学高等学校 K-STEAM類型
授業企画 : 広島工業大学高等学校 教員
授業企画サポート : デジタルファブリケーション協会
当社ではSTEAMカリキュラムの進行支援をしています。詳細・お問い合わせはこちら


